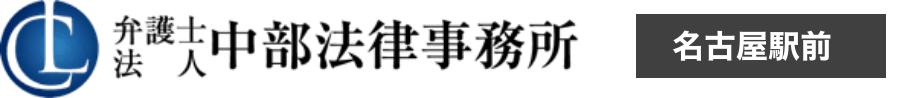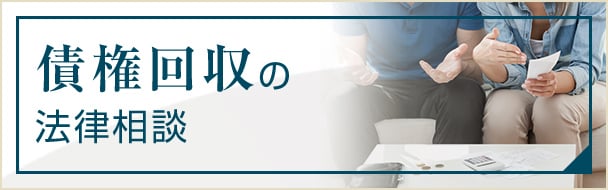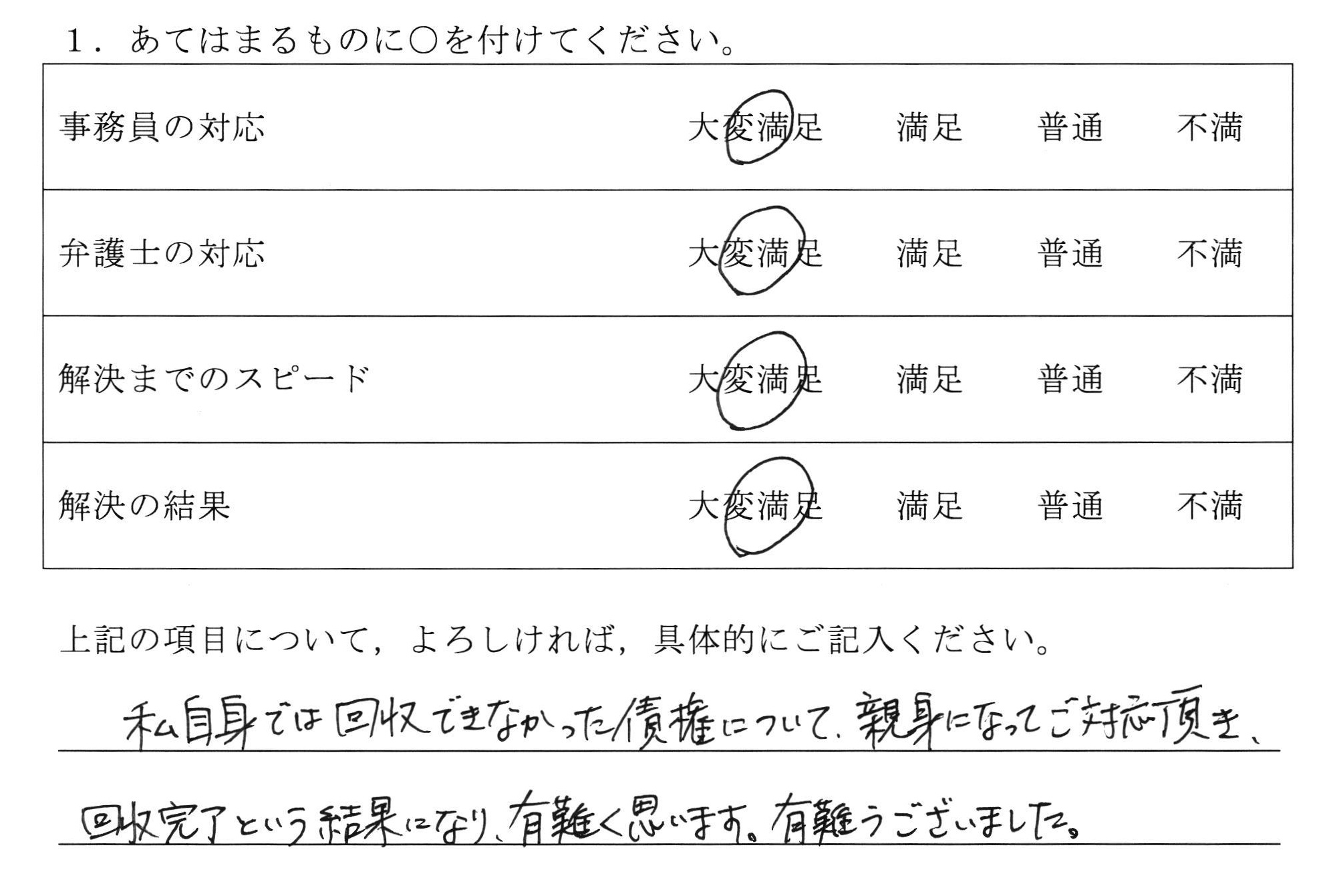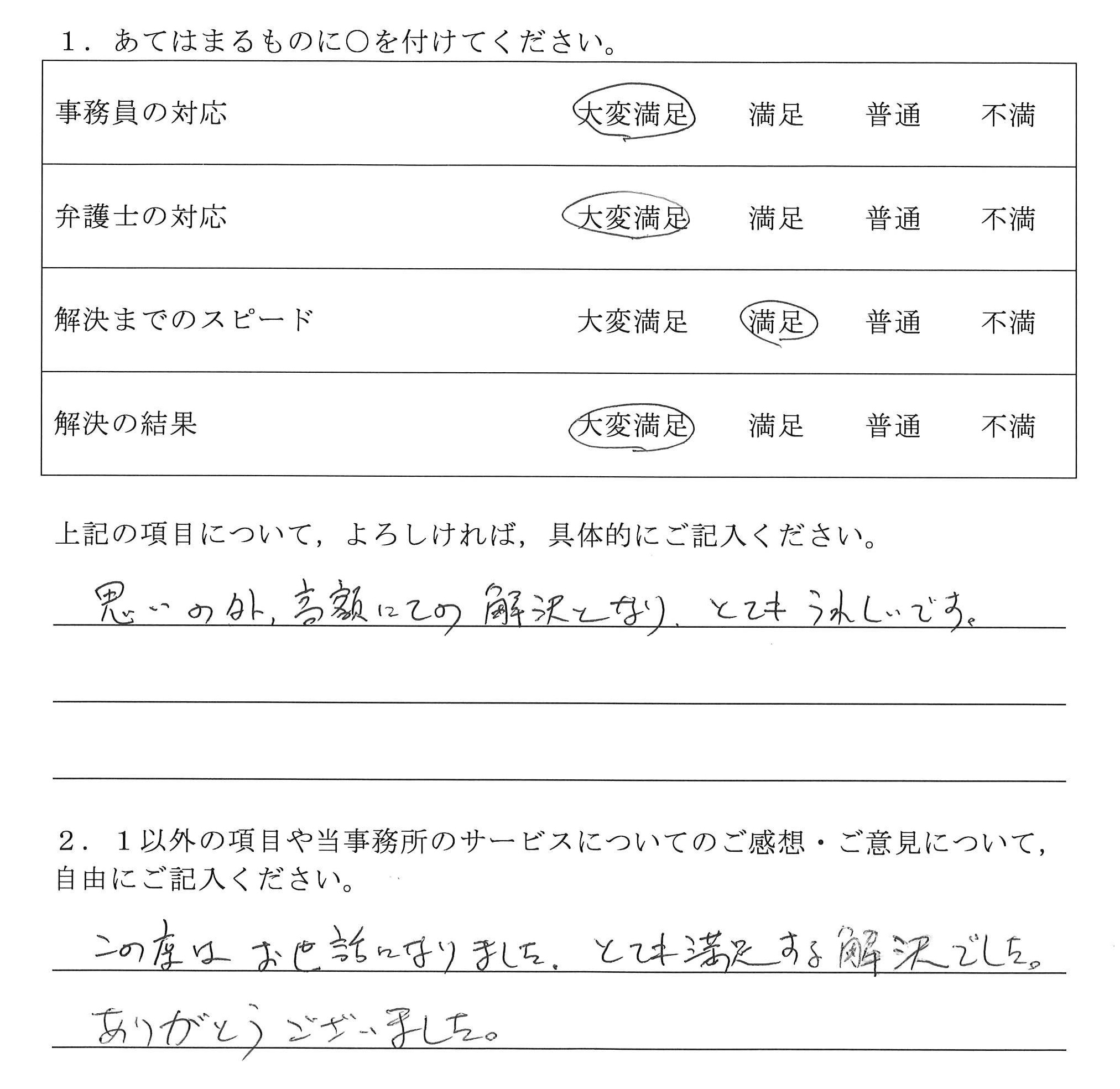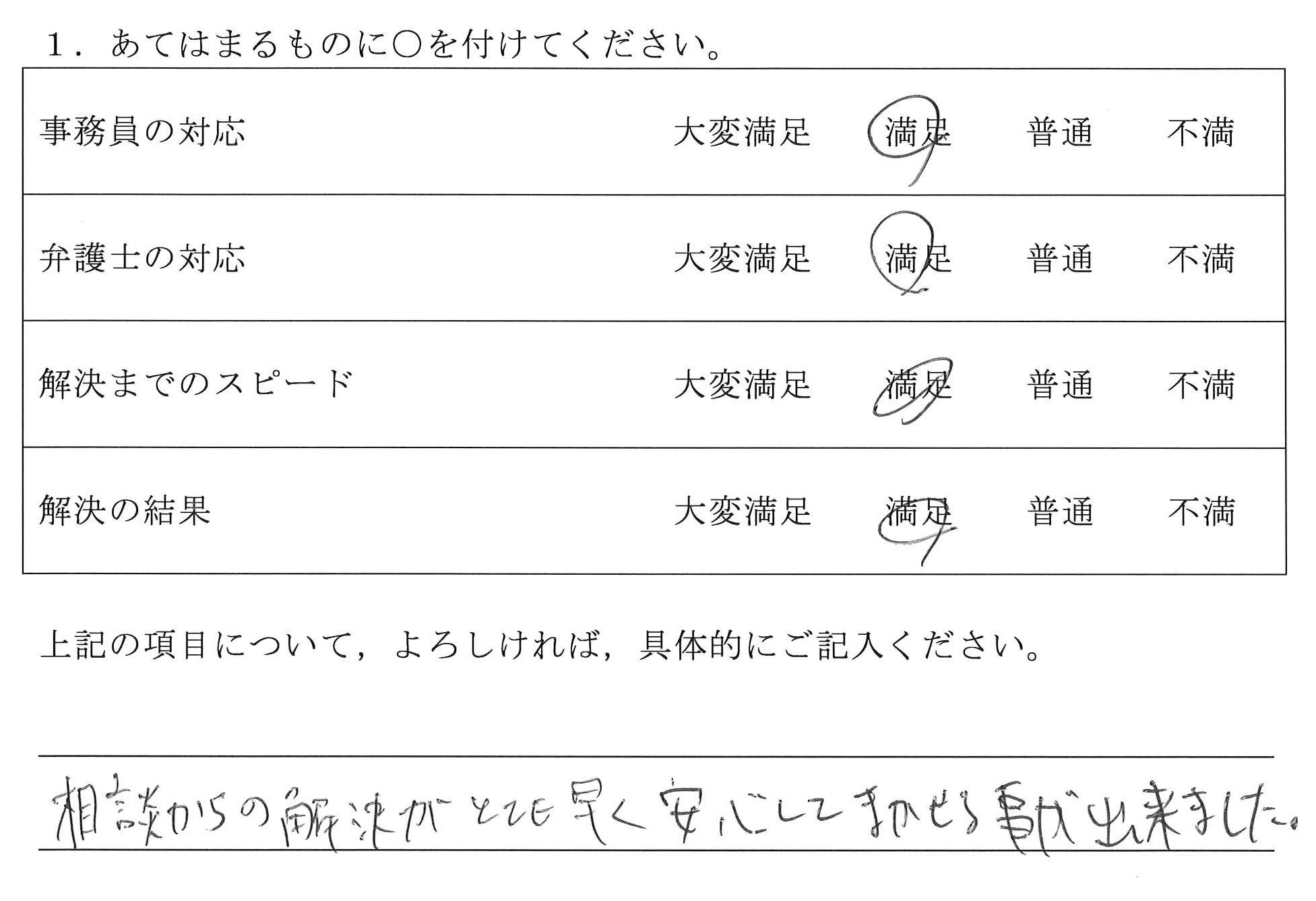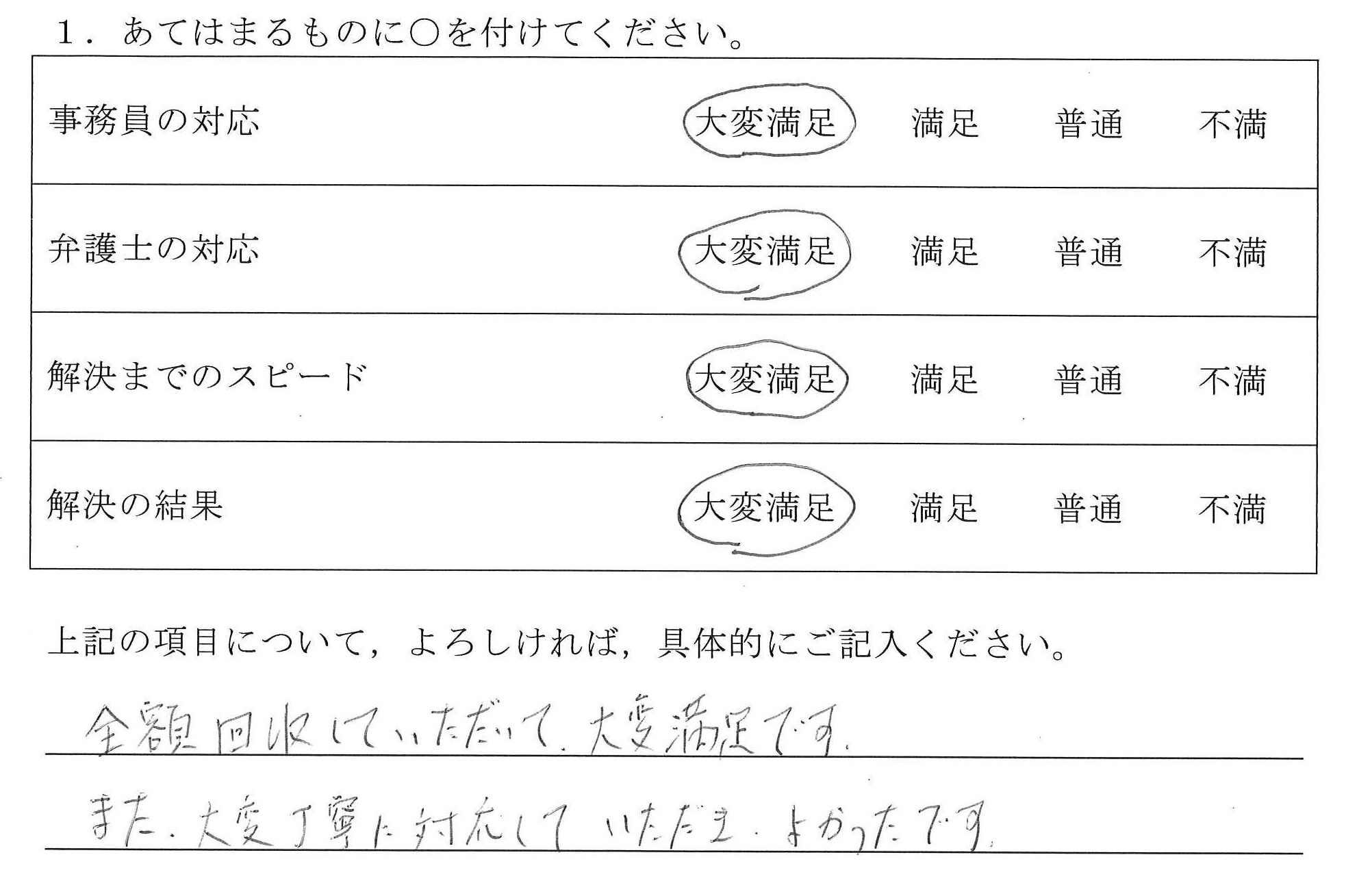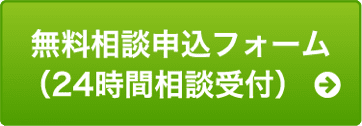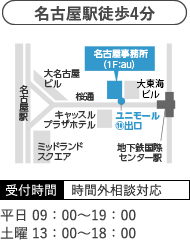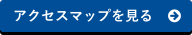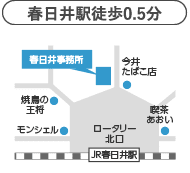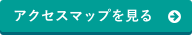交渉
| 弁護士がご依頼者様の代理人として交渉し、債権回収を行う | |
|---|---|
| 着手金 | 10万円(税込11万円) |
| 報酬金 | 現実に回収した金額の16%(税込17.6%) |
別途実費がかかります。実費はあらかじめ概算額の予納金1万円をお預かりし、事件終了時に精算します。
請求額が300万円を超える場合は、別途お見積りいたします。
事案により、着手金ゼロの成功報酬型でお受けできる場合がございます。ご相談ください。
訴訟
| 弁護士がご依頼者様の代理人として訴訟を提起し、債権回収を行う | |
|---|---|
| 着手金 | 10万円(税込11万円)~御見積 |
| 報酬金 | 現実に回収した金額の16%(税込17.6%) |
別途実費がかかります。実費はあらかじめ概算額の予納金をお預かりし、事件終了時に精算します。例えば300万円を請求する場合、裁判所に納める印紙・郵券で3万円弱かかりますので、交通費等の実費を考慮し、予納金4~5万円をお預かりします。
遠方の裁判所に出廷する場合、別途日当(1期日4時間以内3万円(税込3万3000円))がかかります。
強制執行(差押え)
| 弁護士に強制執行(差押え)手続きを依頼する | |
|---|---|
| 着手金 | 1申立につき5万円(税込5万5000円) |
| 報酬金 | 現実に回収した金額の16%(税込17.6%) |
別途実費がかかります。実費はあらかじめ概算額の予納金をお預かりし、事件終了時に精算します。
弁護士が執行に立ち会う場合、別途日当(1期日4時間以内3万円(税込3万3000円))がかかります。
事案により、着手金ゼロの成功報酬型でお受けできる場合がございます。ご相談ください。
財産開示手続・第三者からの情報取得手続
| 弁護士に財産開示手続・第三者からの情報取得手続を依頼する | |
|---|---|
| 着手金 | 1申立につき5万円(税込5万5000円) |
| 報酬金 | 無料 |
別途実費がかかります。実費はあらかじめ概算額の予納金をお預かりし、事件終了時に精算します。
弁護士が財産開示期日に質問を行う場合、別途日当(1期日4時間以内3万円(税込3万3000円))がかかります。
弁護士会照会は1件5000円(税込5500円)です。ただし、弁護士会照会のみのご依頼は承れません。